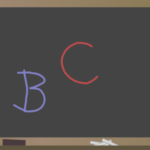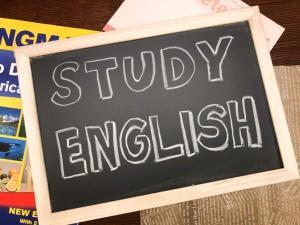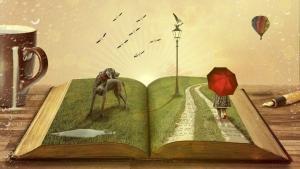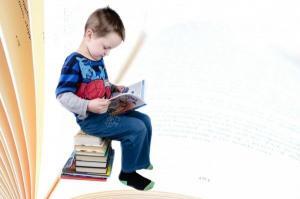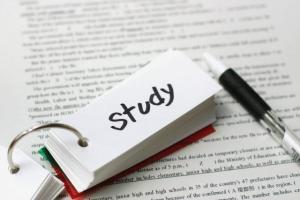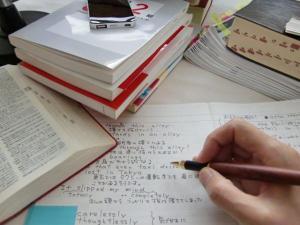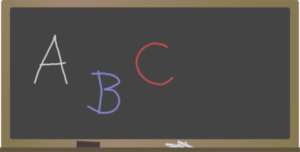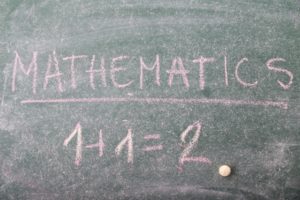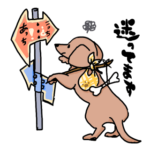
家庭教師や塾講師、さらには大学でのセミナー指導やTAを経験してきた私が思う
”数学を勉強しても成果が上がらない人”
”逆に絶対に伸びるだろうなというという人”
それぞれの特徴を考えてみました。
数学ができる人とできない人の違いは別記事にあるので読んでみてください!
合わせて読みたい・数学が苦手な人の特徴 何故数学が出来ないのか?
他にも数学の雑学記事も書いてるのでおヒマな時にどうぞ
ここが違うぞベスト3!
この人は絶対に数学が伸びるなと思う生徒の特徴は主に3つあります。逆に言えば数学が伸びないと思う人はその逆を行っています。それがこちら。
- 覚えるところは覚えている
- 自分で考えながら解こうとする
- パターンに落とし込みすぎていない
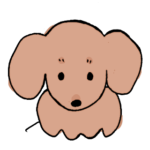
1.覚えるところは覚えている
中学数学、高校数学を勉強していくと意味が分からなくてもとりあえず覚えなければ先に進めない範囲があります。
例えば中学数学でいえば、なぜマイナス×マイナスがプラスになるのかを考える苦労とそれが理解できた時のメリット、一方でその事実を単純に覚えてしまう時間的メリットを比較すると、この場合単純暗記したほうが良いわけです。
他にも高校数学で言えば、なぜ微分と積分は互いに逆演算になっているのかということについても、同じことが言えます。とりあえずその事実をしっていれば、問題を解くのに困らないからです。

もちろん私達指導者からすれば、どれだけ難しい式だろうが定義だろうが、あるいは定理であろうが、その意味は伝えますし、直感的に理解してもらうように努めますが、誰しもがすんなり理解できるわけではありません。
そしてその理解の範囲を超えたときに、理解はひとまずおいて単純暗記という方法を取れるかどうか、いわゆる損得勘定のようなものが重要になってきます。
なぜ割り算はひっくり返して掛け算になおすのか、なぜ分数の足し算は通分して計算するのか、考えずにできるような操作であれば必ずしも考えなくても良いということです。
理解に対する一種の諦めが重要だということです。

2.考えながら解こうとしている
次に思うのは、数学が伸びる人は必ず自分の頭で考えながら問題に立ち向かっているということです。
問題を解いたり解説を見ていて困った時に、分からない箇所の特定や原因究明を放棄して、シンプルに分からないという人がいます。なぜ分かっていないかを教えるのは指導者の役割といえますが、どこを分かっていないか自体は自分自身でも見つけられるところです。
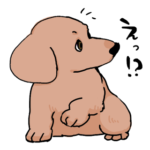
例えば中学数学の合同証明で一行も書き出せない人がいます。そういう人に何が分からないかと聞くと、それが分からないという返事がかえってきますが、これは考えることを放棄している典型です。
どの図形の合同を証明すべきかは問題文に書いてあるということは、どの理論を使って合同証明をしようとするかという選択がまず出てきます。その次に与えられた条件を見ます。
直感でも何でもいいから、とりあえず”いけそうな証明方法”を一度トライしてみて、ダメそうなら別の方法に切り替える。それがダメでも原因を考えて別の方法をとってみる。その繰り返しで証明が完成するのですが、”どこがわからないかが分からないと言う人”は必要な思考の多さに困惑して、思考することそのものを放棄した結果、頭が真っ白になるというわけです。

ダメでも良いから証明してみる。ダメだったら原因を自分なりに考えて証明をし直してみる。最終的に答えが間違っていても、なぜ間違っていたのか考えなおす。日頃からそういったことを繰り返して勉強している人は、ズバリ伸びる人といえます。
答えを見て”なんだそうだったのか”で終わるのではなく、”なぜそうだったのか”を考えるクセをつけることが解決策と言えるでしょう。
一発で答えにたどり着ける人は数学ができる人です。答えにたどり着けなくてももがき足掻ける人は数学が伸びる人です。

3.パターンに落とし込みすぎていない
最後の特徴は、数学が伸びる人はパターンに落とし込みすぎていない傾向がみられます。
例題を解いた後に類題の演習問題を解くという勉強法をとっていたとしましょう。数学が伸びる人も伸びない人も、この勉強法で演習問題は解けるでしょう。ところが章末問題になると、数学が伸びない人はあたふたし始めます。
たとえば2次方程式を解くという問題で、因数分解、平方完成、解の公式という3つの方法を例題と演習で勉強したとします。
章末問題で2次方程式を解けといわれて、色々な形の2次方程式が出てきます。数学が伸びない人は上であげた3つの方法のうち、どれで解を求めればいいかわからず、例題や演習問題を振り返って解き方を真似ます。つまり、パターンを真似ます。

一方で数学が伸びる人はパターンにこだわろうとしません。平方完成したほうが簡単な問題、因数分解したほうが簡単な問題、いろいろあるでしょうが、自分の中で判断基準のようなものがあって、どれをつかって解くかはそれに沿って決めます。
例えば、究極的には解の公式で必ず解けるからひとまず因数分解に挑戦してみようと考えるのも1つの方法ですし、最初から解の公式だけを使うことに拘るというのも一つの方法です。もしくは、平方完成以外認めない人もいるかもしれません。
ある種のパターンを覚えて真似ることは勉強する上でとても大事なことではあるのですが、そのパターン通りでないと解けないと錯覚してしまう人こそが数学が伸びない人であると言えます。
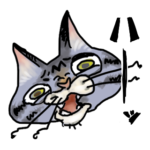
教科書のパターンを真似るのではなく、自分の中でパターンを形成していこうという姿勢こそが、伸びる人の特徴です。
まとめ
数学が伸びる人というのは
の3つを自然にやっています。問題が解ける解けないに限らず、この3つを意識して勉強をすることが、数学力を高める上で大事になってくるでしょう。
数学だけじゃなく英語の勉強記事も書いてるのでよかったら読んでみてください!